関連記事
-

生まれた意味を考える
子どもは親を選んで生まれてくると言う人がいますが、これは本当なのでしょうか。実際そんなことは起こりえません。綺麗事だと私は思ってしまいます。それから、育てられる人のところに生まれてくると言われることも …
2025.04.09
-

借金まみれから再起!お金の失敗から学んだこと
前回のコラムで書いたように、これまで散々お金の失敗をしてきましたが、現在は資産形成ができるようになりました。さらには発達障害専門FP(ファイナンシャルプランナー)として、よそのご家庭のライフプランの作 …
2025.04.02
-

SNSとの賢い距離のとりかた ―「使わされる」のではなく、「使う」コツ (後編)
(※このコラムの「前編」はこちら) 私は、ここ20余年で「インターネットを使うプロ」になったと思います。インターネットに触れてきた長い年月の中で、インターネットの酸いも甘いも噛み分け、サービスの大きな …
2025.02.12
-

冬季うつに注意〜私の症状や対策について
私は、発達障害のASDとADHD、そしてパニック障害があります。最近までは、できる限り元気に仕事や遊びに活発に活動していましたが、12月に入ったころからだんだん寒さが厳しくなり始めたので、うつにも注意 …
2025.01.22
おすすめの記事
-

生まれた意味を考える
子どもは親を選んで生まれてくると言う人がいますが、これは本当なのでしょうか。実際そんなことは起こりえません。綺麗事だと私は思ってしまいます。それから、育てられる人のところに生まれてくると言われることも …
2025.04.09
-

借金まみれから再起!お金の失敗から学んだこと
前回のコラムで書いたように、これまで散々お金の失敗をしてきましたが、現在は資産形成ができるようになりました。さらには発達障害専門FP(ファイナンシャルプランナー)として、よそのご家庭のライフプランの作 …
2025.04.02
-
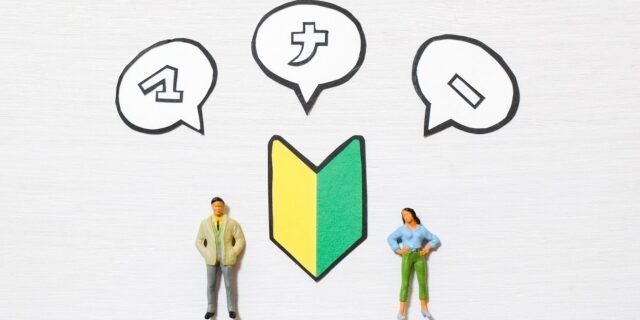
真面目か!
知的障害を伴う自閉症のある息子は特別支援学校高等部卒業後、就職する前、就労移行支援事業所に3年間通いました。その頃の話です。 ある日、その就労移行支援事業所とは別に通っていた通所施設の中に、帽子をかぶ …
2025.03.19
-

本人に障害をどう伝える?いつ伝える?
子どもが発達障害と診断されたり、グレーゾーンだと言われた経験があると、「障害告知」という言葉が頭に浮かびます。 わたし自身も、保育園に息子を入園させる際、誰に、どこまで、どんな風に、伝えたらいいのか分 …
2024.11.13



